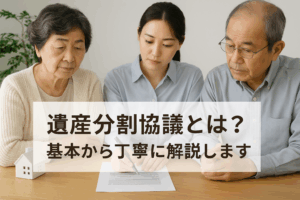制度概要:不要な土地を“国に帰属”させる選択肢
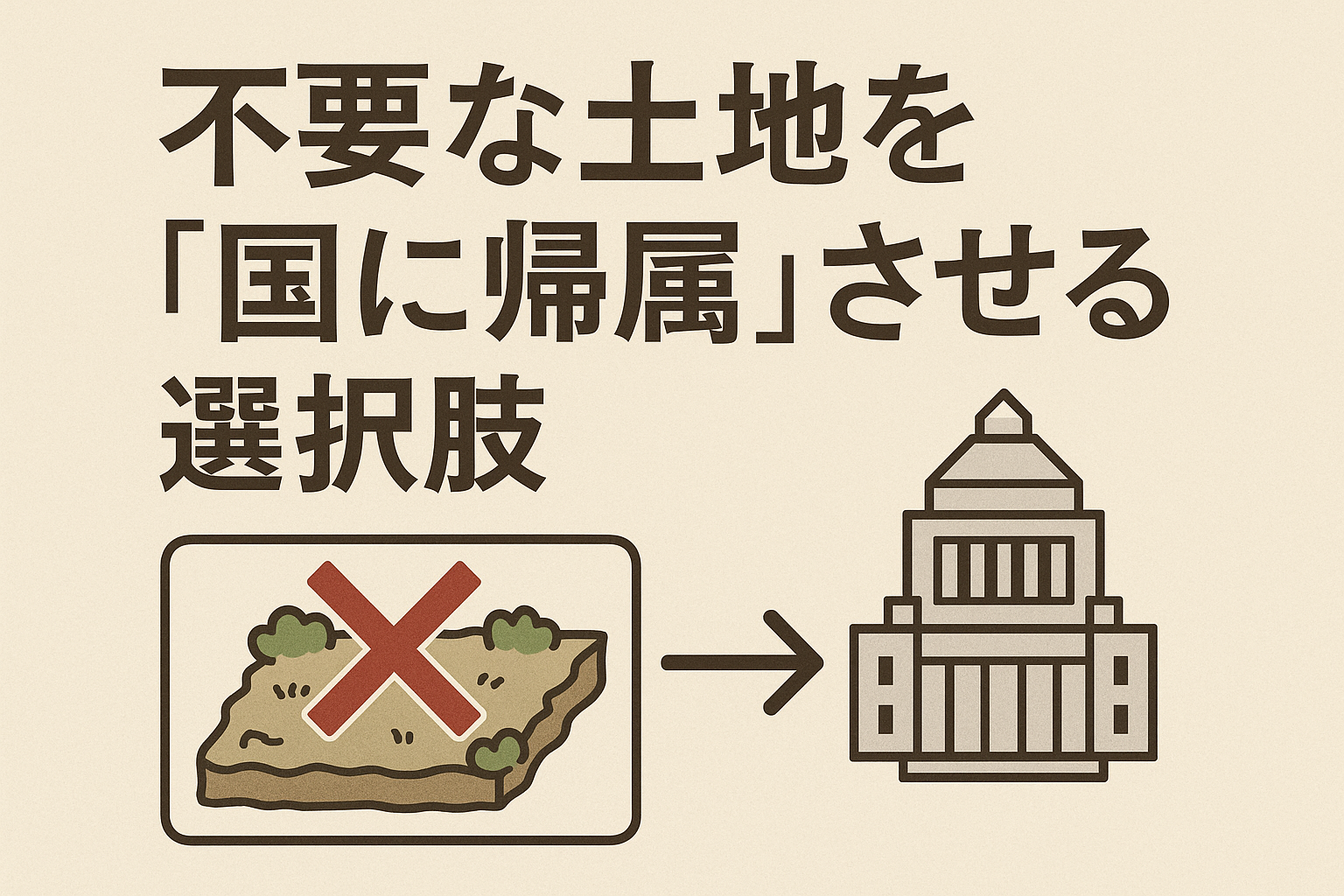
相続や遺贈によって土地を取得したものの、活用計画がなく、売却も難しい土地を所有し続けることには固定資産税・管理コスト・遠方管理の手間といった負担があります。そんな時、相続した土地を国に引き渡して所有権を国庫に帰属させることができるのが「相続土地国庫帰属制度」です。
令和5年4月27日からこの制度がスタートしています。
目次
誰が・どんな土地が対象か
● 申請できる人
- 相続又は遺贈により土地の所有権を取得した個人(相続人)です。法人や売買で取得した人は対象となりません。
- 共有名義の土地なら、共有者全員で申請を行う必要があります。
● 対象となる土地/対象外の土地
制度対象となる土地もあれば、要件を満たさず対象外となる土地もあります。以下が主なポイントです。
対象外となる土地の例(代表的な却下事由)
- 建物が存在する土地。
- 担保権・使用収益権等が設定されている土地。
- 他人が利用予定の土地(公共用道路、墓地など)や境界が明確でない土地、土壌汚染がある土地など。
手続きの流れと費用
① 相談・申請準備
管轄の本局法務局で予約相談をし、土地の状況・書類の必要性を確認します。
② 申請書類提出・審査
申請書・添付書類(位置図・写真・印鑑証明など)を提出し、審査料(例:1筆あたり14,000円程度)を収入印紙で納付。
法務局による書類審査、場合によって実地調査が行われ、要件を満たすか判断されます。
③ 承認・負担金納付・所有権移転
承認された場合、土地の管理費相当額等を基に算定された「負担金」を納付します。宅地・農地・森林等によって負担金額が異なります。
納付が完了した時点で土地の所有権は国に移り、国の有財産として管理されます。
● 費用の目安
- 審査手数料:土地1筆あたり14,000円程度。
- 負担金:宅地や田・畑では面積に関係なく20万円が目安という資料もあります。森林・雑種地では面積・性状に応じて数十万円になるケースも。
この制度を活用するメリット・デメリット
✅ メリット
- 利活用できず手放しづらい土地を処理できる「選択肢」が増える。
- 固定資産税や管理コスト、将来発生しうるトラブルから解放される可能性。
- 所有者不明土地の増加防止という国の方針とも合致。
❗ デメリット/注意点
- 申請・承認まで時間(半年~1年程度)がかかるケースがある。
- 利用できない土地があり、必ず承認されるとは限らない。
- 負担金・手続き費用が発生するため、費用とメリットを事前に比較検討する必要があります。
- 国に帰属した後の土地活用状況は個別には選べない(国管理となるため)。
不動産管理・活用の観点から:相続事業者・オーナー目線でのチェックポイント
- 遠方にある土地、利用予定が全くない土地は「放置リスク」が高いため、この制度を早期に選択肢として検討すべき。
- 売却可能性をまず検討し、売却困難な場合に制度活用を検討するのがセオリーです。
- 相続発生直後に「整理→活用/処分検討」の流れをつくることで、将来の管理負担を減らせます。
- オーナー様への収支報告・活用提案の一環として、「土地処分の選択肢」にこの制度を含めて情報提供可能です。
✅ 全体の要点をまとめたミニ要約
不要な土地を相続した際、売却も活用も難しいときに「相続土地国庫帰属制度」を検討すれば、国に土地を引き取ってもらえ、管理負担や税金負担から解放される可能性があります。ただし、対象土地の要件・費用・手続き期間を事前に確認することが重要です。
投稿者プロフィール

最新の投稿
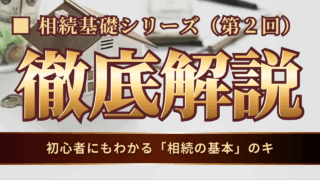 相続お役立ち情報2026年1月8日【第2回】相続人って誰?——家族関係と法律の“意外なズレ”
相続お役立ち情報2026年1月8日【第2回】相続人って誰?——家族関係と法律の“意外なズレ”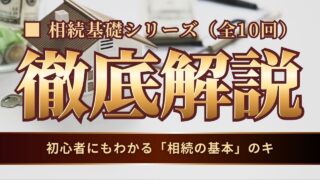 相続登記 名義変更2025年12月7日【第1回目】相続の基本のキ —— はじめてでも迷わない「大事なポイントだけ」やさしく解説
相続登記 名義変更2025年12月7日【第1回目】相続の基本のキ —— はじめてでも迷わない「大事なポイントだけ」やさしく解説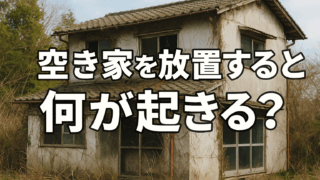 不動産活用・整理アドバイス2025年10月27日実家が「空き家」になったとき、どうする?放置せずに考えたい選択肢
不動産活用・整理アドバイス2025年10月27日実家が「空き家」になったとき、どうする?放置せずに考えたい選択肢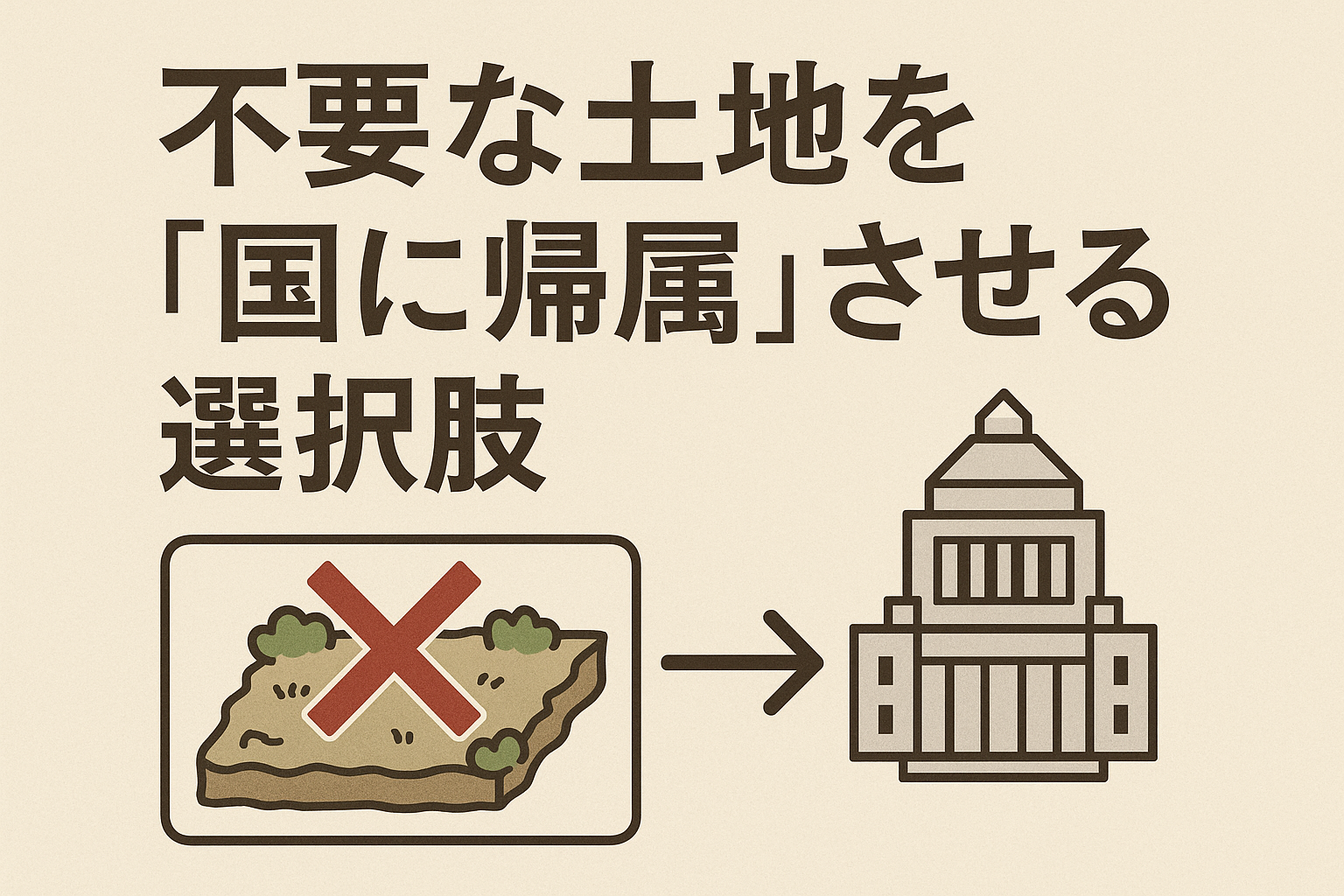 不動産活用・整理アドバイス2025年10月27日制度概要:不要な土地を“国に帰属”させる選択肢
不動産活用・整理アドバイス2025年10月27日制度概要:不要な土地を“国に帰属”させる選択肢